
第75回 9/9 ウィトゲンシュタインと言語(4) 開催レポート
ウィトゲンシュタインと言語(4)
2020年9月9日(水)21:00~22:30
開催レポート
令和哲学カフェ「ウィトゲンシュタインと言語」の4日目となりました。
今回は「意味とは何なのか」というテーマについてWHTを行い、深めていきました。
日本では、「役に立ちたい」と願う人が多くいます。役に立つという考えは、良く思われがちですが、実はとても受動的な姿勢でもあります。その反対である、主体性、能動性を発揮するということは、自分で意味をつくる生き方だと言えます。それが今までも紹介してきた、カント、ニーチェ、ドゥルーズ 、ウィトゲンシュタイン、フロイトに代表される哲学です。
今までは、意味があることに価値がある時代でした。これからは、意味がないことに価値がある時代になります。意味とは、伝統的な意味を全部ひっくり返すことであるとNohさんは解析します。だから、哲学は今までを全て否定することを通して、新しい概念を発見してきたのです。
また、今回もWHTでも活発な意見が飛び交い、何を言っても安心、安全の場であることが伝わる場でした。また、視聴者を楽しませる演出もあり、ディスカッションでは緊張感もありながら、和やかな気持ちにもなれる回となりました。
<質問コーナー>※一部抜粋
Q:nTechでいう「言語の限界」をウィトゲンシュタインはどのように解析し、どのように乗り越えたのでしょうか
A:ウィトゲンシュタインはメタ言語はつくっていない。哲学に言語を取り入れて、その言語の機能を鮮明にした。言語につかまれている世界は本物ではなく、勝手な言語の思い込み。それを「言語ゲーム」と表現した。哲学の対象がなくなってしまう、無知の世界であり、無意味の意味に到達したのがウィトゲンシュタイン。
次回は9月10日(木)21時からです。「ウィトゲンシュタインと言語」の最終回となります。どうぞお楽しみに!
参加者の感想
今日は哲学の歴史が織り込まれた英雄産業の解説が印象に残りました。日常の意識と思考に哲学的な考え方が実はすでに組み込まれていることを感じます。またそれらを整理することができる視点からみられる令和哲学のわかりやすさ!(白窓軒さん)
「意味とは?」日頃からよく使う言葉であり興味深いテーマでした。WHTを見ていて参加者の皆さんが回を増す毎に生き生きと発言され、和気藹々とされる姿が美しいなと思いました。(sanaさん)
役に立つ・・・ドキッとするフレーズです。目に見えるものの意味価値から、みえないもの、無意味の意味の時代。本当に新しい時代について語り合っていくことが尊いなと思います。目にみえるものに反応するとすべてが受動的に思えてきました。ありがとうございました。(たまいちゃんさん)
出演者の皆さんが俳優に見えました。人の役に立つエンジンで生きていた今までの自分にNO出しせず、これからは主体的にいろんな役割を演じて楽しめばいいんだと思えました。クラウドファンディングの達成もおめでとうございます!(しまさん)
たくさんのご感想をお寄せ頂き
ありがとうございました。
もっとアンケートを見たい方は
令和哲学カフェコミュニティサイトをご覧ください。
またのご参加をお待ちしております。
コメント ( 110 )
トラックバックは利用できません。


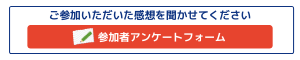



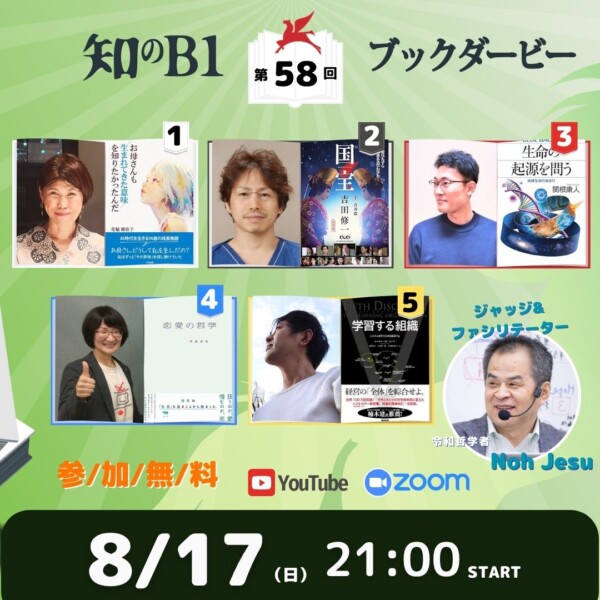



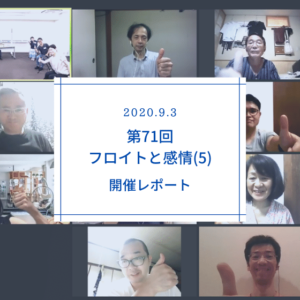
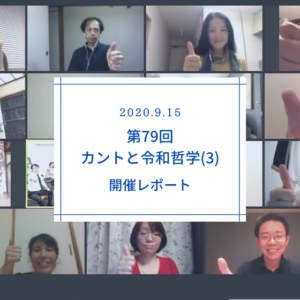

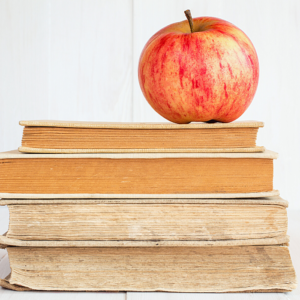
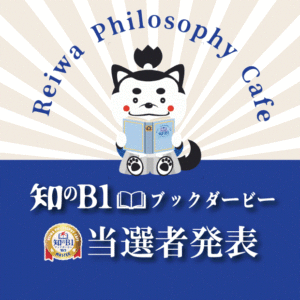
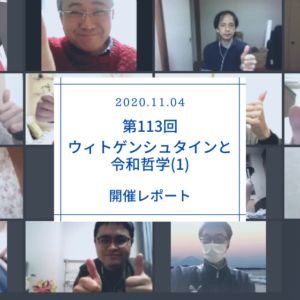
маркетплейс аккаунтов продать аккаунт
продажа аккаунтов соцсетей https://marketplace-akkauntov-top.ru/
гарантия при продаже аккаунтов профиль с подписчиками
магазин аккаунтов аккаунты с балансом
маркетплейс аккаунтов маркетплейс аккаунтов соцсетей
продажа аккаунтов соцсетей платформа для покупки аккаунтов
услуги по продаже аккаунтов https://pokupka-akkauntov-online.ru
Account exchange Ready-Made Accounts for Sale
Account Trading Platform Website for Buying Accounts
Accounts market Account Trading Service
Account Selling Service Account Buying Platform
Account Selling Platform Account Catalog
Secure Account Purchasing Platform Account exchange
Social media account marketplace https://buyagedaccounts001.com/
Guaranteed Accounts Account Trading Platform
Buy Pre-made Account Buy accounts
Buy Pre-made Account Website for Selling Accounts
Account Store https://socialmediaaccountsale.com
accounts market social media account marketplace
buy and sell accounts guaranteed accounts
gaming account marketplace ready-made accounts for sale
account sale accounts marketplace
verified accounts for sale marketplace for ready-made accounts
account buying service account selling service
buy account purchase ready-made accounts
account buying platform account acquisition
buy and sell accounts account market
find accounts for sale guaranteed accounts
account buying service account buying service
account buying service accounts marketplace
account trading service account buying platform
account selling service https://social-accounts.org
database of accounts for sale account trading platform
account trading platform accounts market
buy accounts https://social-accounts-marketplace.org
account trading platform account trading service
account buying platform buy-social-accounts.org
online account store profitable account sales
website for selling accounts accounts market
buy and sell accounts account exchange
database of accounts for sale account catalog
guaranteed accounts account market
marketplace for ready-made accounts sell pre-made account
account acquisition accounts marketplace
ready-made accounts for sale accounts marketplace
account selling platform account market
account exchange service https://accounts-offer.org/
secure account sales https://accounts-marketplace.xyz
online account store https://buy-best-accounts.org
account exchange service https://social-accounts-marketplaces.live
ready-made accounts for sale https://accounts-marketplace.live
account trading service https://social-accounts-marketplace.xyz
account marketplace https://buy-accounts.space
secure account sales https://buy-accounts-shop.pro
buy account https://accounts-marketplace.art
find accounts for sale https://social-accounts-marketplace.live
account market account marketplace
marketplace for ready-made accounts https://accounts-marketplace.online
sell pre-made account https://accounts-marketplace-best.pro
маркетплейс аккаунтов https://akkaunty-na-prodazhu.pro
покупка аккаунтов https://rynok-akkauntov.top/
купить аккаунт kupit-akkaunt.xyz
маркетплейс аккаунтов соцсетей https://akkaunt-magazin.online
купить аккаунт https://akkaunty-market.live
маркетплейс аккаунтов соцсетей kupit-akkaunty-market.xyz
площадка для продажи аккаунтов https://akkaunty-optom.live
продажа аккаунтов маркетплейсов аккаунтов
маркетплейс аккаунтов https://akkaunty-dlya-prodazhi.pro
покупка аккаунтов https://kupit-akkaunt.online/
buy facebook ad account https://buy-adsaccounts.work
facebook account buy buy facebook advertising
buy facebook profile https://buy-ad-account.top
facebook ad account buy https://buy-ads-account.click
facebook ad accounts for sale https://ad-account-buy.top
buy aged facebook ads accounts buy fb account
buy facebook account facebook ads account for sale
facebook ads account buy https://buy-ad-account.click
buy old facebook account for ads https://ad-accounts-for-sale.work
buy google ads https://buy-ads-account.top
buy adwords account https://buy-ads-accounts.click
facebook accounts to buy buy aged facebook ads account
google ads agency accounts https://ads-account-for-sale.top
google ads account buy https://ads-account-buy.work
adwords account for sale https://buy-ads-invoice-account.top
buy google ads accounts https://buy-account-ads.work
google ads accounts for sale https://buy-ads-agency-account.top
buy google ads verified account https://sell-ads-account.click/
buy verified google ads account https://buy-verified-ads-account.work/
buy business manager account https://buy-business-manager.org
google ads account for sale https://ads-agency-account-buy.click
verified business manager for sale https://buy-business-manager-acc.org
buy verified facebook https://buy-bm-account.org/
buy business manager account https://buy-verified-business-manager-account.org
buy facebook business managers https://buy-verified-business-manager.org/
business manager for sale https://business-manager-for-sale.org/
facebook verified business manager for sale facebook bm account
unlimited bm facebook https://buy-bm.org/
facebook bm for sale https://verified-business-manager-for-sale.org/
buy business manager buy fb bm
tiktok ad accounts tiktok ads agency account
tiktok ads account buy https://tiktok-ads-account-buy.org
buy tiktok ads accounts https://tiktok-ads-account-for-sale.org
tiktok ads account buy https://tiktok-agency-account-for-sale.org
tiktok ad accounts https://buy-tiktok-ad-account.org
tiktok ads agency account https://buy-tiktok-ads-accounts.org
tiktok ads account for sale https://buy-tiktok-business-account.org
tiktok ads account buy https://buy-tiktok-ads.org
buy tiktok ads account https://tiktok-ads-agency-account.org
buy a facebook ad account account marketplace guaranteed accounts
buy facebook ads accounts secure account purchasing platform account marketplace